電話照合で突破口——樋口楓さん、観察審査ホラーで判断を固め視聴者と共闘
電話照合で突破口——樋口楓さん、観察審査ホラーで判断を固め視聴者と共闘
配信冒頭、樋口楓さん(でろーん)はインディーの観察型ホラー/審査シミュレーション「That's Not My Neighbor」を選び、住人になりすます“ドッペルゲンガー”を見抜く門番役に挑んだ。ルールは、顔写真やID、居住フロアなどの情報を突き合わせ、矛盾があれば拒否、整合すれば入場を許可するというもの。さらに備え付けの電話で住人側へ照会できるのが要点で、樋口楓さんは「いわゆる入国審査みたいな感じ」と位置づけ、予備知識は最小限のまま現場対応で臨んだ。 チュートリアルが強調する「住人の外見に最新の注意」「どんな小さな間違いも見逃してはなりません」という点は、配信全体の緊張感を貫く指針となり、観察と判断の積み重ねが見どころを形づくった。 まずは“初見”での等身大の反応が軸、という独自角度を宣言した。
観察と照合が噛み合った瞬間
配信は、チュートリアルの「電話を使用できます」という指示を受け、照合という“第二の目”を積極的に活用する流れで加速した。 住人情報を読み上げながら「同居人にちょっと電話してみます?」と声に出して工程を可視化し、リスナーと手順を共有した判断が最初の山場となる。 中盤では、情報に矛盾が見当たらないケースで「うん通すか」と決断し、通過を許可した場面が象徴的だった(https://www.youtube.com/watch?v=3sjTzrXxz1Y&t=2617)。 そこから、書類を忘れたと主張する申請者への対応、外見の微差をどう扱うかなど、ケースごとの迷いが生む緊張と緩和が続く。終盤、誤審の可能性に気づいて振り返る一言が響き、最後の挨拶では翌日の雑談予告まで含め、視聴体験を生活の延長線に着地させた。
本配信は、にじさんじの多様な個性が光る“観察と会話”型の見せ方に沿い、謎解きの手順をリスナーと共有する設計が際立った。シリーズ作ではない単発選定ながら、観察と通話照合のサイクルがテンポを作り、初見の緊張を娯楽化している。配信は約2時間で、視聴は約2.7万回という到達。 作品の詳細はSteamの公式ストアで確認できる(https://store.steampowered.com/app/2674850/Thats_Not_My_Neighbor/)。同時に、番組や今後の活動はにじさんじ公式(https://www.nijisanji.jp/)と、樋口楓さんの公式チャンネル(https://www.youtube.com/@HiguchiKaede)からたどれる。にじさんじらしい“自由度の高い寄り道”も含めて、鑑賞の入り口は広く用意されていた。
一面の決定打—電話照合で迷いを断つ
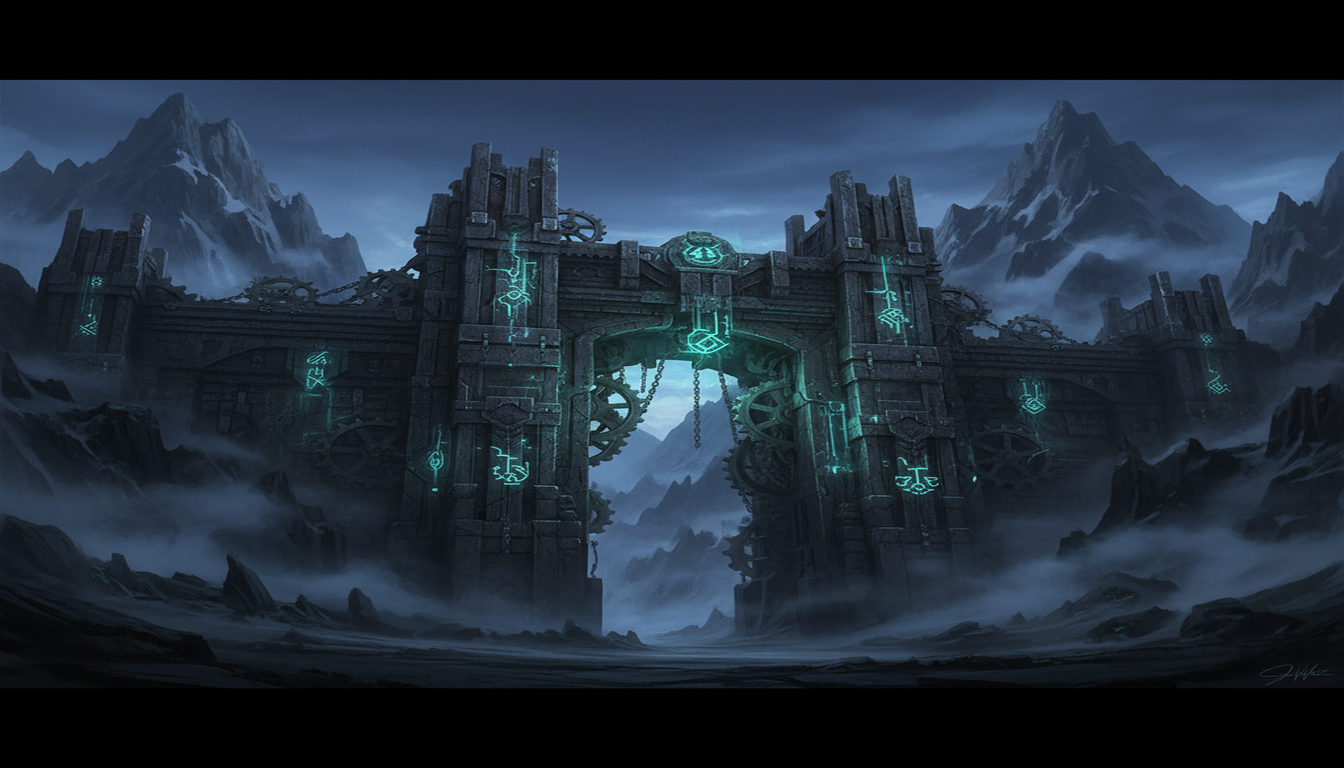
決定的だったのは、書類と外見が一致してもなお、最後の一押しとして電話照合を差し込んだ判断だ。チュートリアルの「電話を使用できます」という案内を受け、樋口楓さんは「同居人にちょっと電話してみます?」と自分で“手順の声かけ”を行い、判断プロセスを視聴体験に転写した。 このとき、画面上の資料フォルダをめくるしぐさや、端末へ手を伸ばす一連の操作が、門番という役割のリアリティを補強する。 通話の応答内容とIDの整合が取れた瞬間に通過を許可し、結果として“通す/拒む”の線引きが曖昧になりがちな局面をクリアにしたのが印象的だった(https://www.youtube.com/watch?v=3sjTzrXxz1Y&t=1335)。 以降のケースでも、この照合一手が迷いを鎮め、流れを前に進める役割を担っていった。
転機を刻んだ三場面—疑念、微差、余白
まず一つ目は“日常に生まれた疑念”の読み上げだ。「ドッペルゲンガーと結婚したかもしれない」という相談文を淡々と確認し、私情を排して記述の矛盾だけに焦点を当てた瞬間。これは以降の判定で、感情ではなく証拠を重ねる姿勢を固めた転換点となった(https://www.youtube.com/watch?v=3sjTzrXxz1Y&t=2507)。 二つ目は“微差への厳しさ”。「たった1日帽子をかぶらなかっただけで…?」とつぶやきつつ、別件では「明らかに生やしてるヒゲやからな」と微差を重大な要素として扱い、線引きの基準を調整した。 三つ目は“余白の遊び”。山場の合間にカードゲームへ寄り道し、「このカードゲームめっちゃおもろい」と気分を切り替えた。これが緊張と集中のバランスを取り、終盤まで観察力を保つ下支えとなった。
見守りと声援—チャットが背中を押した秒針
観察の現場を支えたのは、チャットの細やかな反応だ。開始早々「どっちが偽物かなあ」と期待が灯り、微差が気になる場面では「目が違うねぇ」と注視点が共有された。 電話照合を選んだときには「電話ないすぅー」と声援が重なり、チェック工程の手応えが視覚化された。 樋口楓さんも「いいね 慣れてきたね」と自らの進行を評価し、観察→疑念→照合→判断というサイクルを言語化。 さらに「意外と覚えてるかもな」と住人の顔認知に言及したくだりは、視聴者との共犯感覚を強める合図になった(https://www.youtube.com/watch?v=3sjTzrXxz1Y&t=4879)。 こうしてコメントの“視点の重ね書き”が、画面外の補助線となり、判定の迷いを小さくしていった。
誤審からの立て直し—気づきが精度を上げた
終盤にかけて浮上したのは、誤審を受け止める冷静さだ。思わぬ仕様に「はぁぁ!? 聞いてねえし!」と驚きつつも、そこで止まらず検証の手数を増やして再発を防いだ。 そして「入場拒否したドッペルゲンガーで…本物やったってことか」と振り返り、外見の“オシャレの幅”を見落としかけた点を自省した。 コメント欄にも「ジジイおしゃれしただけやったか」と苦笑が残り、視点のアップデートが共有された。 この経験以降、樋口楓さんは微差の評価を即断せず、電話照合や住人リストの参照で補強する運びに切り替える。結果、終盤の判定は安定度を増し、配信の締めに向けて流れを整えた(https://www.youtube.com/watch?v=3sjTzrXxz1Y&t=5247)。 コメントの「おあいこやね」という受け止め方も、配信空間の温度を和らげた。
次回への視界—サクッと推理から広がる余白
クロージングで、樋口楓さんは「推理系のゲームしたいなと思って」と選定の意図を語り、「このゲームはなんかサクッとできて面白かった」と総括した。 さらに「明日はねお昼に…新しい味買ったんで それを食べる配信をしようかな」と次回の具体的な予定を示し、重い余韻を引きずらず日常へ帰る導線を置いた(https://www.youtube.com/watch?v=3sjTzrXxz1Y&t=7245)。 雑談の小ネタも「この日のために旧みそ金置いてた」と添え、視聴者の生活時間に寄り添う予告で締めている。 今回の“観察→照合→判断”の型は、より本格的な推理ノベルや脱出系でも活きると示唆される。にじさんじの柔軟な企画性と、樋口楓さんの言語化力が重なれば、次回も“共に考える”体験が続くだろう。
